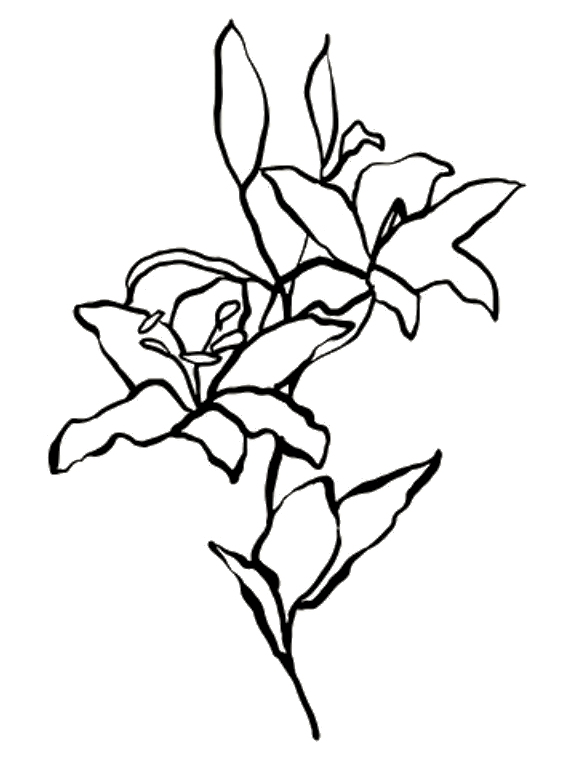
ねじれの位置
缶の温度は外気とすっかり同調してしまっている。
投げた缶はゴミ箱の縁に当たって転げていく。
甘ったるい清涼飲料水を好まない彼の喉は乾いていて、ゴミを捨て直している馬鹿を横目に、唇を舌先で湿らすに留まった。
えりの伸び切ったTシャツの裾を片手で煽る××の、うなじから生まれた汗の粒が背中を通って腰へと転がり落ちる。
機械的な店員の声と無機質な電子音、煌々と嘘を許さないLEDの光、真っ直ぐアイスコーナーへ去っていく片割れ。
無個性の白いビニール袋には、ぬるくなり掛けた缶ビールが二本と薄い小箱が入っている。
溶けだした甘い液が棒を伝って手を汚す。
東京の夜空は反射する雲が鈍光を放っている。
ジャラジャラと財布の中で小銭が踊っている。
何かが棲みついている○○の黒い眼差し、そのとき××の中に生まれた衝動は、暴力性に近いけれど異なるもの。
××はうっすらとまぶたを上げて、黒い襟足からのぞく肌の匂いを肺いっぱいに吸い込む。乱れた呼気を吐きながら舌先で転がる汗を舐めとり、薄い皮膚の下に脈打つ血の流れを思って、溢れた唾液をまぶすように噛みしだく。
壊れゆく予感を胸の奥にしまう時の密かなざわめき。
どれだけつなぎとめても戻らない欠片、どこへでも付きまとう過去の匂い。
寝ぼけたまま手に取った箱から新しい一本を抜き取ろうとすれば、それはあっさり潰えた。
眠らない東京砂漠に登って八年が経ったが、だんだんと摩耗していく中、凍てつく早朝のベランダで新しい箱を吸っているときだけが生きている。
湯船の縁の灰皿目掛けて振るった灰が外れて、湯を汚し、思わず舌を打った。
「」
いつまでも耳の奥にこびりついて離れないあいつの乾いた声、目の笑っていない薄い笑み。
なにげない言葉の切れ端が過去を連れてくる。
欠け落ちた何かを拾いあげようと、掻き集めて掻き集めて気づけば八年が経っていた。
くだらない会話が絶えたとき、相手の考えていることが読めなくて、そこに横たわる空気だとか、去っていく車のヘッドライトの残光とか、誰かを家へと運んでいく終電の四角い窓の並び、探るような眼差し、ランドリーのガタガタと眠気を覚ますような音、なにか物言いたげな唇、そういうものをただ互いになぞって、なぞるだけしかしなかった。
そうして今夜も何ひとつ本質に触れぬまま、××はシンクに凭れて無感情を視線に乗せる。
水滴がシンクの底を叩く音が鈍く耳に響く。
この憂鬱なキッチンで茹でたパスタ、言わぬ言葉を絡めて咀嚼した。
風に舞い上がるレシート、広告、にんじん百九十円。アパート1LDK十万。
無理じゃない、無理なんかじゃない、そう言い聞かせて、欠けた部分をテープで止めるような日々を過ごしている。
八年かけて知ったのは、どれだけ肌を合わせて奥深くまで入り込んでも欠け落ちた何かは欠け落ちたまま、互いの何ひとつも分かり合えはしない、そんなことだった。
七月の教室に吹き込む風がけやきの梢を揺らし、風に膨らむ白いカーテンに木漏れ日がゆらゆらと揺れていた。ページのまくられるパラパラという響き、校庭から響くホイッスルの音が眠気を湛えた教室の空気を微かに切り裂き、
『でも ほんとうの幸せってなんだろう』
『僕 まだわからないよ』
『二人で一緒にほんとうの幸せを探そう』
音読する○○の声がその合間をたゆたっていく。
珍しく起きて耳を傾ける××は何かを考えるまなざし、そのときすでに薄暗い未来の予感は始まっていて、その延長線上にどれだけ近くにいようと埋められない今があること。
ふたり、どこまでも一緒にいたところでねじれの位置は直らないまま。